|
�@9:05����R�J�n�B
�@�������c��R�ő�̓�ł���B
�@�ቺ�͂܂��ɋ}�X�̃K����B���������ɂȂ�قǃg���b�L�[���B�o��͋��˂��������������A����͋��|�ł���B
�@������������m�ߤ�אS�̒��ӂ��Ȃ��牺���BI�N����납����S������悤�ɋC��z���Ă����B
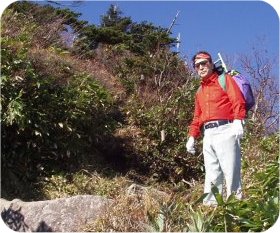
�@�����̖@�����v���o�����B
�@�d�Ԃ��}��Ԃ����Ƃ����������q�͑O�ւȂ�������B�Ȃ��H�@�����Ă���d�Ԃ̒����A�����X�s�[�h�ő����Ă���̂��B�d�Ԃ͎~�܂��Ăओd�Ԃ̒��͑����Ă���B��q�͎v�킸�O�̂߂�ɂȂ��ĉ����ɂԂ���c�c�B
�@�d�Ԃ͂���ł����B���̐�ǂȂ�H
�@�s���ӂő������点�ł�����A�u�����Ƃ��ƁI�v�ł͂��܂Ȃ��B�����̃A�N�Z�����ǂ̂悤�Ɏ~�߂��炢���̂��B�Ƃ�����Ƥ����Ȋ댯���҂��\���Ă���̂��B
�@�Ƃ��ǂ��A����̂����Ƃ���ŗ����~�܂��ď��U��Ԃ�B�m��ʊԂɂ��Ȃ艺��Ă���B���������̈���ऑ����Ȃ�Ƃ��܂Ƃ܂����������B���̈������Ȃ��������ɕς��͂Ȃ���������ɂꤋC�������������Ă����B
�@�����~��ł���B���i�����j�₩�ȗz�C�͒���̂Ƃ������オ���Ĥ�����ŃV���c�ł������B
�@10:10��ƕ��ɉ��藧�B
�@���ʂ�2�{�͂����������B����ł�I�N�͏^���Ă����B
�u�S�z���邱�Ƃ��Ȃ������ˁB�債�����椂��݂́I�
�@�t�ɔނƂ��ẮA���i�̊����̖@�����}�u���[�L���Ȃ��炾����A�R�j�Ƃ͂�����ς������낤�B
�@���̈ƕ��A����͖��̒��������B���E�s�ǂŤ���܂ɂ��J���o�債�����炢���B
�@����Ȃ������̂��B�ǂ̕����������܂ł��ׂČ��ʂ���B�����͍g�t�^�����肾�B����͕c��R�̗Y�p���P���Ă���B
�u�����Œ��߂āA���オ�厼�����ƁA���ꂪ�z���ł��邾�낤�I�@�~�X�e���[���ˣ
�@I�N���A���グ�Ȃ���A�Ԃ₭�B
�@�������ɒ���ɗ����đS�e������A
�@�w�܂�Ō~�̔w�̂悤�ɂ��̙ˁi�ڂ��j��Ȑ}�́i���������j���������Ă���x�i�[�c�v��u���{�S���R�A32"�c��R"�v�A�������Ɂj
�@���������B
�@��������̒��߂͂����}�o�̎R�`�i�����j�Ť�s�Ă���͂܂����������H�t�Ǝ���X�������Ȃ�i�D�ł���B
�@�O�f���̎��̏��q���C�ɓ������B���p����B
�@�w�����c�ꂪ���}�ȎR�ł������礂����̉��R�Ƃ��ĕ����Ă����ꂽ���낤�B�Ƃ��낪����͐l�̖ڂ���i�Ёj�����ɂ͂����Ȃ��B�����Ĉ�̎R�������礂��̖����킸�ɂ͂����Ȃ������������Ă���B�����ꂽ���ͤ�ǂ�ȂɉB��悤�Ƃ��Ă��A���ɂ��������̂ł���x
�s�c��R�ɓo�����B�����̂��Ƃऒr���i���Ƃ��j�������t�i�������݂��j�ऑS���m���Ă�I�t
�@����̋}�s�����x�����グ�Ĥ�D�z�������ݏグ���B�@�@
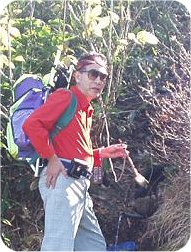 �@10:20��������Ƃ�������ɒ����B�N��������i�Ƃ��j��`���ė��ꗎ���Ă���B �@10:20��������Ƃ�������ɒ����B�N��������i�Ƃ��j��`���ė��ꗎ���Ă���B
�@�₽���Ă������������B�Ђ��Ⴍ�ʼn��x�������肵���B
�@���̂����褗��ɂ悭�o���������Ť���̖�������B
�u����킩��H�v
�@�ނ͍��ɂԂ牺���Ă�����̂�������B
�u���T�m�킾��B���܂̂Ƃ���S�R��Ȃ����礂悩�����ˣ�@
�@10:50��_�y����B
�@�����Ɣ����łŕ����Ă���B����ł����͂ق�̂�B���������炱���܂ł͓o��Ԃ��ł��������������薟���ŋ�ɂȂ�Ȃ������B
�@�Ȃ�Ƃ���₩�ȎR�������B���̓�����̓V�C�Ɋ��ӂ��悤�B
�u�ǂ���炱�̒��q�ł����������I�@���݂̂���������v
�@�ނ͂����ڂ��������グ�Ĥ���R�I���܂ōD�V�ȊO�͂��肦�Ȃ����Ƃ�ۏ����
�@���炭���₩�ȉ��肪�����B�R���̂��܂��܂�䍁i�͂��j�����Ƃ���o�Ă����B
�@���̃����f�B�A���A�q���b�e�̎G���Q�A�����A�����U��A�c�c�c�c
 �@11:15�����������B �@11:15�����������B
�@�߂��ɂ��ꂢ�ȍg�t������B
�u�i�i�J�}�h����v
�@�ނ͒T���Ă����̂�����ƌ������l�q���B�ڂ��͂��Ȃ��Č��Ƃ��B�i�i�J�}�h�̗t���ς͂���Ȃ������̂��B
�@����̓����ɗ��Ĥ�o��ŋx�Ɠ����ꏊ�ɍ������낷�B����킽����������߂̂������̍���Ɣ�ׂ�͖̂�邾�B
�u����Ȃ̎����Ă��Ă��
�@�w���{�S���R�x�Ɓw�c��̒n�}�x��������Ƥ
�u�ڂ��͂���
�@�ނ͈ӊO�Ȗ{�����o�����B�w�S�̂����A���{���̏W�x
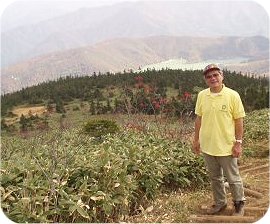
�@����ɂ��Ă����̌����炵�B��l�Ƃ����S�ɋA���Ĥ�����オ��B�͂邩�������̍g�t�тɓ͂��Ƃ��褍�鎼���ʼn̂����V�{���Z�̍Z�̂����x�����������B
�@���m�ł��牺�m�łցB�X�̗l�����ǂ�ǂ�ς���āA���R�т��牺�E�ɋ߂Â������Ƃ��i�F�������Ă���B�I�I�V���r�\���N�}�U�T���A�w�������Ȃ��Ă����B�ς��Ȃ��̂̓K����Ƃʂ���݁B
�@��납��I�N���b��������B
�u�����Ԃ�O�A�����̘A���Ɠ����̂�������n�C�L���O�����B���̎����ꂪ�����o��������x�O���p�قɊ�邱�ƂɂȂ����B����x�O����̏��������Ǥ���������ˁB���M�Ȃv
�u����Łc�c�H�v
�@�ڂ��̋������āA�b���B
�u���w�Z�̐搶�Ť�N���u�����̂Ƃ���ɏd�ǂ����B�葫���S�R���߂ɂȂ���������B���ꂩ�炪�ނ̐^�������ˁB�M�����ɂ��킦�ĕ�������������G���`���B���ꂪ��}�Ȃ��肩��|�p���B�葫�����R�Ȑl���͏I���������ʂ̐l���������J������v
�@�O������Ȃ���A�ڂ��͎��܂��Ă���B
�u����ł����悤���̂Ȃ礔ނ͏����낤�ˁB�ނ̐��_�͂Ɩ��邢�������́A�ڂ���̑z�����E��y�������Ă����
���`���̊G�拹�łӂ��݂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����G�q�@
�@������10��15���B���܂���́A�k���N�ւ̝f�v��Q��5�l�����{�ɓ������Ă���͂����B����铹�X���̂��Ƃ����Ȃ�b����������������ł͊�������B
�@�s�v�c�̈�B���̖������Ȃ��B
�@
�@����͓ܓV�ɕ��Ɩ����������班���͔[��������������͂��̍D�V��z�C�ɂ��Ĥ�Ȃ��H
�u1�A2�����O�Ȃ炯���������₩��������B�o�[�h�E�I�b�`���O���邭�炢������B�~�Ɍ������ĕʂ̂Ƃ���ֈړ������悤���ˣ
�@�ނ���u������Ȋ�����ĈԂ߂Ă��ꂽ�̂��c�c�c�c
�@�s�v�c�̓�B�o�R�҂����ɏ��Ȃ��B
�@
�@�O���͑̈�̓��ŁA�j���B�ǂ̎R���������Ԃ����낤�B�Ƃ��ɒ����N�̎R�����M�́A�ЂƂ���ڂ����ُ�ɂ��������炢�����礂����Ēm��ׂ��B
�@���̍g�t�̎����3�N�O�ɉ������̐�ꃖ���֍s�����Ƃ����i��26�b�j�2�N�O�ɓ��k�̈��B���ǎR�i��41�b�j���B�q���R�i��42�b�j�֍s�����Ƃ��ऎR�̌i�F�ɂ�����̐���Ȃ�߂��Ă���悤�������B
�@���܁A�߂��̒J��x��q���R������R��O��R������R�c�c�͂��������B
�@���{�S���R�Ɩ����t�������ŕ]���ɂȂ�̂ɁB�c��R�����̖����t���Ă���̂ɁB������10���̂��܁A������߂����Ƃ͂�����Ԃ̕S���R�ł�����̂ɁB
�@����̓o��ग\�z�ɔ����Ă���Ȃɓ��₩�ł͂Ȃ������B�q���b�e�̍��݂悤�Ƃ����Ăओo�R�Ґ��ł͑��R�̔�ł͂Ȃ����낤�B
�@�����̉���͉��l�ɏo������낤���B10�l����l����l���������x���B
�s�c��̌i�F�͂ڂ������̂��߂ɂ������t�Ȃǂƌ֑�ϑz�ɂӂ����Ă����̂��B����������ƌ�������Ĥ
�s�J��x�q�̉����̈ꂩ�ł�������֗��Ă����t
�@�]�v�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����B
�@���m�ł̔~�x�e���Ť�����N�j��6�l�̃p�[�e�B���i�x���͂�ł͂��Ⴂ�ł����B74�ɂȂ����j���̒a���j���B
�@�ޤ���D���������Ȃ���A
�u���ꂵ���ˁB�Ɠ��Ɩ��A����ɖ��̗F�����B���N�����ŏj���Ă�����ł���
�@�L�O�ʐ^���B����������B

�@14:05��a�c�����o�R�����B

�@5���Ԃ����ĉ��肽�B�ڂ��͂���ł��s�悭������I�t�����A�ނɂƂ��Ă͕��i��3�{�̒x�����B�u���肪�Ƃ��I�v�Ƃ����\���ł��Ȃ��������A�ӂɔ����Ĕނ͖ʔ������Ƃ������B
�u��������������������ˁB�N�Ɋ��ӂ����
�@���ł����̂��ǂ����B���A�܂��k�ł��Ȃ������̂��B���̏؋�������B����ނ���͂����������i�����Ɍf�ځj�ɂ���ȓY����������������B
�@�u��Z�̌��r���̂���B�����̌�肠�肪�Ƃ��
�@15:00�A�z�㓒��w�B�A��घa�c��������40���Œ������B
�u�����ł���������I�
�@�ނ͋��������~�߂����������莫�ނ����B����1��2���̊������A�܂��]�C����߂ʂ����ɐÂ��ɐU��Ԃ肽�������̂��B
�@���̂܂�z�V�����œ����ցB
�@���Ȃɍ������낵�Ă܂Ԃ������B��i�܂Ȃ��j�̉��̓X�N���[���ɕς��B2���Ԃ̎v���o�����X�ƌ�����B
�@�R���̏H�i�F��o�艺��̕����Ɩ������I�N�Ƃ̐s���ʌ�炢�c�c�B
�@�����Ƃ肵�āA�����������Ȃ����Ă��邤���Ɉł������B
�@�c�c�c�c
�u�����ł���I�
�@�ڂ��J����Ƥ�ׂ�̋q���h��N�����Ă���Ă����B
|